横山 彰人 著
第21章 他人の顔
光が自分のこぶしでドンドンと床や壁を激しく叩くようになったのは、いつからだろう。そればかりではなく、光、光と呼んでも振り向かなかったりあまり言葉も話さなくなった。また、以前のように目を輝かせて笑うこともなくなった。咲子は、そのうち治るだろうとあまり気にしていなかったが、床を叩く回数や叩く時間も長くなって、さすがに心配になった。一度医者に行こうと思ったのは、買ってきた育児書を読み、二歳を過ぎた光の成長の度合が気になったからだ。周りに同じ年齢の子供を持った友達もなく、比較することも出来ず迷った末、武夫にはとりあえず相談しないで、近くの小児科クリニックへ行くことにしたのだった。
小児科医院から自宅に戻り、しばらく何も手が付かず、ぼんやりテレビを見ていた。思わず提言のレポートを思い出し、慌ててテレビを消した。今度は、シーンとした静寂な空間に耐えきれない自分に出会った。
できれば武夫に話をしたくなかったが、事態がそれを許さなかった。
「光のことで話をしたいので、出来るだけ早く帰ってきて下さい」と、携帯でメールを送った。返事のメールは無かったがその夜武夫にしては早い九時頃に帰り、光が眠った後ダイニングのテーブルで、今日先生から言われた診断結果を全て話した。
武夫はこの数ヶ月毎日帰りが遅く、光との触れ合いも少なかったせいか、光の変化を気がついていないようだった。それほど仕事に没頭していたということも言えるし、同時に家族を振り返る心の余裕すらなかったということだろう。こんな暮らしを夫不在の母子家庭という言い方もするが、家族があっても家庭はない日々だったことを思い出し、涙が滲んだ。二人の間に空白の時間が流れた。
外は、かなり烈しい雨が降っていた。窓ガラスに当たって流れる水滴は、部屋の灯に照らされ、キラリと輝いては糸の様に流れ落ちていった。ガラスは断熱性のある二重ガラスで防音性も高く、そして建物が鉄筋コンクリートゆえ、雨足が強いのに全く雨音がしないことに、何か不自然な気がした。
雨の降る日は、京都西陣の家のように雨の音を聞きたい。風の吹いている日は、吹きすさぶ風の音を聞きたい。マンションは自然の音が聞こえない住まいという箱なのだと思った。
武夫の言葉を待っている間にそんな事をボンヤリ考えるほど、全て話した後一気に気が抜けた。
武夫は話を全て聞き終わってから、テーブルの上に置いてある日本小児科学会からのレポートに目を落していた。話の途中から武夫の目は怒りの目に変わり、こぶしが小刻みに震えているのが分った。殴って気が済むなら、殴られてもいいと思った。
光がこうなった原因は、一日中光と二人で過ごす時間の中で起ったものだ。二人で過ごすということは、公園や外で遊ばせる事もテレビを見る時間にしても、全て咲子の責任のもとに行われた。これは言い逃れ出来ないことだが、子育ての経験もなく、これまでの咲子の人生で乳幼児に触れることもなく抱いたことすらないのでは、光の症状を初期の段階で気が付くのは無理な話だった。
しかし武夫の反対を押し切って社宅から出、マンションを選び、現在の間取りで妥協したのも咲子だったし、武夫には全て事後報告だった。
武夫は突然、せきを切ったように、
「咲子、光をこんな病気にしたのは一体誰だ。全ておまえが原因を作ったんじゃないのか。俺が一生懸命会社勤めをし、残業している間に何があったんだ。この小児学会のレポートに書いてある、二歳以下の子供にテレビを長時間見せるなとか、乳幼児に授乳中や食事中テレビをつけないようにしようとか、ほとんどの事は俺が会社に行っている間で、咲子が責任を持って対処すべき時間内でのことじゃないか」
どうしようもない苛立ちをぶつけた。
「このマンションに移るまでの社宅では、光は順調に成長していたんじゃないのか。専業主婦として、母親の役目を果たしていると思っているのか」武夫は声を荒げ、咲子に詰め寄った。さらに、「光の運動不足、テレビ、ビデオの見過ぎ、友達がいない、そしておまえが選んだベッドのおかげで、家族が一緒に寝れない部屋、落ち着かない間取り、その行き着いた結果が光の無気力症候群か。咲子、説明してくれ」咲子は黙ってうつむいたまま、何か言おうとしても言葉が出てこなかった。確かに武夫の言う通り、社宅での光の成長は順調だったし、全て幸せを実感できる毎日だった。
しかし光のため、家族の幸せのためにマンションを購入するといいながら、選択の基準としてきたものは大人の尺度でしか見てこなかったのではないか。高層マンションからの眺望、夕陽が見える、駅や会社にも近くて快適で便利。そして資産価値が高くすぐ売れるマンションといった、どれもこれも大人の目線で考えステータスを満たすことばかりで、子供のために大切なことは何も考えてこなかったように思う。
しかしそれは当然武夫にも責任は向けられるはずのものであるが、なぜか言えなかった。
「咲子、何か言ってくれ。考えてみれば、京都のお父さんから援助を受けなければ、こんな事にならなかったんだ。床の間付の和室とか、すぐ売れる物件を探せとか、金も口も出すから希望した間取りを買えなかったんだ。息子が無気力症候群で、その病気を治すには生活を見直す以外に無いなんて、人に恥かしくて言えないよ。光をいい学校に入れるために頑張ってきたのに、スタートの段階から人より遅れてしまった事、分っているのか」武夫は、最初言わないでおこうと思っていた父親の資金援助のことを、感情が高まり、つい気が付いたら言ってしまっていた。父親から援助が無ければ、大幅にマンション購入は遅れ、また買えたところで今より狭く、通勤時間も二時間以上になってしまうと分っていたので、内心喜んで受け入れたが気持ちは複雑だった。
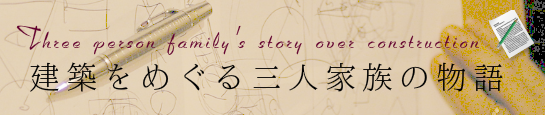
 第20章 人工の街並
第20章 人工の街並