横山 彰人 著
第14章 リフォーム
ようやく契約をしたのは、初めてマンションを探し始めた日から一年と二ヶ月目の十二月上旬、街にジングルベルの音楽が流れている頃だった。渋谷の文化村界隈や道玄坂の街路樹には、ブルー、白、赤の様々なイルミネーションが輝き、東京で一番といわれるファッションの発信基地渋谷の街が、さらに一段と光輝く季節だった。
咲子は、ようやくマンションが決った安堵感と共に、二ヵ月後にはこの街から離れる寂しさと、幸せに過した日々を思った。
引越しまでの間、壁紙の貼り替えだけのリフォームだったが、たくさんの見本やサンプルの中から、夢を膨らませながら選ぶ作業は楽しかった。
光に手がかからなくなったら、咲子はインテリアコーディネートの資格も取りたいと思っていたし、自立して仕事もできればと思っていた。住まいのインテリアをお客様にまかされ、床、壁、天井の素材を決め、カーテンの色を選び、自分の世界を理解して貰えたら、どんなに楽しいだろうと考えるとワクワクした。
「光ちゃんはどんな色がいいの」と言うと、様々な色や絵の中から光が指をさすのは動物の絵や、青い空に浮かぶ風船の絵だったり、そんな光との会話のやりとりも楽しく、完成するまで何回かマンションに通った。
その度に壁紙を貼る職人さんに、ペットボトルや温かなコーヒーやお菓子を持って行った。職人さんはみんな良い人で、仕事をやりながらの勝手なおしゃべりも楽しかった。近くに住んでいる職人さんらしく、「奥さん、こんな眺めの良いマンションで暮らせるなんて幸せだね。昔この辺りは海で、よく泳いだり潮干狩りをしたもんだよ。まさか海が埋め立てられて、こんな大きなマンションがたくさん建つなんて、信じられないよ」
五十代後半に見える職人さんによると、このあたりはかつて漁村で、住んでいる人は近海の漁業や海苔の養殖で生活をたてていたそうだ。一変したのは昭和三十年代頃から始まった高度成長期に、東京湾の埋め立て工事が進んでからだという。
ここは埋め立て地だったんだと初めて知った。つまり都心に通勤する人のための新興住宅地でありベッドタウンでもあることが、京都西陣に生まれ殆ど何代も前から住んでいる人ばかりの中で育った咲子には、不安と期待が入り交じった気持ちになった。
「引越し前の壁紙の貼り替えぐらいで、お茶やお菓子をわざわざ持って来てくれるなんて、ありがたいよ」と口々に言われ、マンションを褒められた上、差し入れも喜ばれ、気恥ずかしかったが嬉しかった。
食べ物の差し入れは、咲子が小学生の頃西陣の家を手直しするため大工さんが出入りした時、母がいつもやっていたことだ。三時のお茶や、夕方過ぎる頃には温かいうどんを出したり、咲子もよく母に手伝いながら一緒に職人さんの休憩時間にお菓子をもらって食べたものだった。
職人さんをねぎらうのは当り前のことだと思ってやっただけのことであったが、母に感謝した。
工事は、今まで貼られていた壁紙を取り除き、下地の調整をしてから新しい壁紙を貼る、それだけの作業であるが、それでも職人さんの腕の差が出る。剥がした後の下地の調整をどれだけしっかりするかによって、仕上りが変わってくるし、壁紙を貼ったつなぎ目の技術や処理の仕方によって完成時の美しさや、それ以上に年数が経った時の美しさの維持状態が変わってくる。
出来れば金額の差額を出してもいいから、ビニール製の壁紙という化学製品を使った材料ではなく、板貼とか塗り壁といった体に良い自然の素材を使いたかった。しかし、三倍以上価格が高いこともあり、諦めた。
それでも剥がした後の何も無い無機質の空間に、自分と光が選んだ壁紙が貼られていくのを見るのは楽しかった。
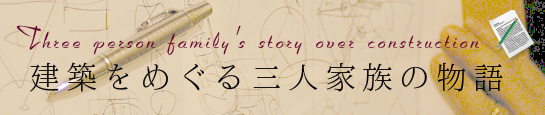
 第13章 手付け
第13章 手付け