横山 彰人 著
第8章 川の字の空間
待望の子は男の子だった。そして名前を「光」とつけた。男なら光とつけようと決めていたが、咲子にとって自分の子供は他の誰よりも輝いて欲しかったし、その「ひかり」によって周りも明るくする、そんな思いもこめられていた。
京都の父も口には出さないが男の子を望んでいたのは、母から聞いていた。光が実家の後継になる訳ではないが、マンション購入資金を出してもらうこともあり、父の意にそえる形になって、それなりに安堵した。
出産する病院は社宅から近いほうがいいという判断から、渋谷の駅の近くで、桜の名前がついた「桜坂」の中ほどにある、大きくはないが清潔そうな明るい病院を選んだ。窓からは、すでに葉桜になった桜の枝に青葉がよく茂り、窓下の賑やかな通りを見なければ、社宅の窓から見る風景とよく似ていた。五月の風に葉が揺れて、陽の光にキラキラ輝いていた。
ベッドが置かれている部屋は、出産する母親がリラックスできるような雰囲気で、壁には印象派の複製の油絵や、見舞いに来る家族や来客用のいかにも高級そうなソファーが置かれていた。薄いベージュの塗り壁、窓にはオフホワイトのレースのカーテン。まるでファッション雑誌に出てくるような部屋だった。
そんな部屋をわざわざ下見して選んでくれた武夫の心も嬉しかった。武夫は光を抱き上げ嬉しそうに、ヒカル、ヒカルと言って窓辺から外を見ている。
二人の後姿、その先には青い緑の葉が風に揺れ、そしてその先にはさわやかなスカイブルーの空があった。咲子はなぜか涙がにじんだ。
光が家族に加わり、新しいマンションに移って過す日々を思うと、今がこれまでの人生の中で一番幸せではないかと思った。もっともっと幸せになるために、明日から頑張ろうと心に誓った。
光をベビーカーに乗せ買い物に出ると、社宅の口うるさい奥様達も寄ってきて、「かわいいね、お父さん似かしら」とか、近くの小児科病院やベビー服の安い店を教えてくれたり、光のおかげで以前より話相手も増えた。
何よりも助かったのは、社宅の中庭にある砂場では、同じ年頃の乳幼児がいつも遊んでいて、自然な形で仲間入りさせてもらったことだった。
以前子育ての本を読んだとき、「公園デビュー」に失敗し、いくつもの公園を捜し歩いたり、母親が話相手がいなくノイローゼになった例が書いてあり、不安を持っていただけにホッとした。その点は、社宅という同じ会社に勤めている家族の集まりゆえのことだと思い、感謝した。
しかし、子供を遊ばせていながら母親達が話している話題は、相変わらず夫の昇進の話や噂話であることが、耐えられなかった。
武夫は徐々に会社で責任も重くなり、仕事の量も増えて帰りも十二時近くなることも多くなったが、無理しても週二日ほど夕食時に帰ることを自分に課しているようだった。
早く帰る日は、駅に着いたら電話をくれることになっており、十五分後に帰ってくるのを見計らって、光を抱っこして二階のベランダに出る。
遠くから武夫が、満面の笑みを浮べ手を振りながら近づいてくる。「光、パパよパパよ」と指をさし示すと、光もパパとは言えず手を振り上げ、「バグバグ」と体全体を動かしながらはしゃいで喜びを表現している。近づいたところで「パパおかえりなさーい」と声をかける。幸せを感じるひとときだ。
夕食の料理を整えている間、光とハイハイをしたり楽しそうにあやしている。襖を開けると全ての部屋が見える間取りは、後を向いて料理をしていても、二人が何をしているか気配で全てわかる。
その日の食卓は、腕によりをかけ武夫が好きな料理が並ぶ。武夫はビールを飲み、咲子はその日だけはワインをいただき、光を中心にその日の出来事やこんな言葉を話したとか、とりとめのない話が楽しかった。
同じ空間の中で着替えをし、食事をし、お酒を飲み、そして家族三人で光を真中に川の字になって寝る。今風の個室中心の間取りと比べ、廊下がなく部屋と部屋がつながっているから、全ての動作がひとつの空間の中でできることが、家族がより家族らしく生活できるという意味で好きだったし、何よりも家族の一体感が感じられた。
武夫の家も咲子の家も、夕食はいつも家族が揃っていたし、父親が仕事で遅くなっても帰るのを待って夕食をとった。一日の話がはずみ、電灯の下で家族揃っての食事。あたり前だと思ったその頃の日常は、いま思い出すとかけがえのない家族の団欒だった。そんな平凡だが温かな家族の団欒を、咲子は望んでいた。
しかし、仕事が忙しく会社中心に生活せざるを得ない武夫は、無理をして週二回。その二回すら咲子には言わないが、同僚や上司から嫌みをいわれていることは、容易に想像できた。どこまで無理が続けられるか分らないが、親子が川の字になって体を休める時、しみじみ幸せを感じ、こんな日がいつまでも続けばいいなといつも思った。
一日も早くマンション購入のため動きたかったが、さすがに光を連れての行動は首もすわっていない状態では無理だった。本格的に動き出したのは、その年の十月、窓から見る欅の葉が少し色づく頃だった。
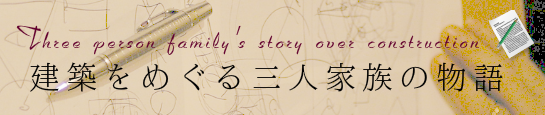
 第7章 親の援助
第7章 親の援助